ウチのオコメ
お天気と土と稲に向き合い、楽しみながら取り組む米作り。農業のイメージを変えること、そして亡き父の味を再現すること、それが次の世代へのギフトだと信じて。
清らかな水、澄み渡る空、時折顔を出す虹、そんな自然豊かな長野県松本市でお米を作っています。私たちはこの自然の恩恵を大切にした農法を取り入れています。もちろん減農薬にも取り組んでいます。畔を彩る一面のアップルミントは害虫から稲を守ってくれています。

特にこだわっているのは土作り。楽にお米を作ろうと考えれば一度化成肥料を撒けば良いですが、あえて私たちは、堆肥をはじめとする数種類の発酵有機肥料を使います。その後も稲の成長の様子を見守ります。土を見つめるその先には微生物の声。微生物が住みやすいよう、全てをコントロールしながら丁寧に稲を育てています。収穫したお米は、火力を使わず、自然乾燥機の中で1ヶ月間、自然の風でじっくり乾燥させます。そのように育てたお米は一粒一粒が大きく、ふっくらしていて、口に含むとほんのり甘い、極上のお米に仕上がります。

お米の美味しさを保つことにもこだわります。お米は“生物”ということを意識されている方は、そう多くはないのではないでしょうか。管理方法が杜撰(ずさん)だと、せっかくのおいしいお米の味が劣化してしまいます。丁寧に育てたお米をおいしく召し上がっていただきたい、との思いから、収穫したお米を大型冷蔵庫で低温保存しています。精米する際にはお米に糠(ぬか)が残らないよう、精米前に1日程度常温にさらしたのち、低温で精米します。

農業のイメージも変えたいとも思っています。農業ってもっとカジュアルでもいいのではないか、そうすることで若い人の農業離れも抑止できるのではないか、そう考えています。農業に携わる際の服装はあえてカジュアルに、トラクターもピンク色に塗装しています。田んぼアートにも挑戦しています。それぞれの個性を尊重しながらも、一方で美味しいお米を作りたい、という共通の信念は、太い一本の柱として中心に据えています。


どうしてそんなに米作りを愛しているのか。それは、今は亡き父が作ってくれたお米の味が忘れられないからです。“冷めても美味しい米を作る”、父がこだわったお米の味は、今も私の脳裏にしっかりと焼き付いています。父が亡くなってから農業を継ぎましたが、当初は父の味を再現できませんでした。どうしてもあの味を再現したい、試行錯誤の末にたどり着いた味は、なんと業界最高峰の国際大会にて金賞を頂くに至ります。(受賞歴の詳細はこちら)

“父がこだわった味は間違ってはいなかった、今度は私たちが次の子供達に引き継ぐ”。
父の無邪気で温かい笑顔を瞼に浮かべながら、今日も田んぼに向かいます。


 コシヒカリ
コシヒカリ
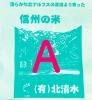 金賞米
金賞米
 風さやか
風さやか
 つきあかり
つきあかり
 ブレンド米
ブレンド米